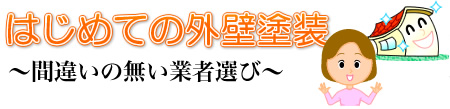屋根塗装。塗料サーモアイSiとケレンの、終わりなきカンケイ
2015年10月1日
現在一般的なスレート(コロニアル)屋根だけではなく、トタン屋根の塗装にも遮熱に効果的な塗料のひとつ「サーモアイSi」が効果を発揮します。これは大きな分類では2液タイプとも呼ばれ、主剤(大缶)と硬化剤(小缶)を調合して使用します。
さらにサーモアイSiはシリコン樹脂を成分に含む弱溶剤タイプの塗料で臭いが少なく、施工中ご近所に迷惑をかける心配もありません。シックハウス症候群への配慮にも有効です。
現場の職人がこうした特性をよく理解し、丁寧な仕事をすることで、遮熱性能、環境性能、健康性能などサーモアイSiの持つ多くのメリットがいっそう際立ちます。
こちらは窓周りの木部に用いる下塗り塗料です。
木製窓枠など劣化しやすい箇所を保護する塗料で、職人が塗料面の状態を良く観察しながら、丁寧な刷毛塗りを行ないます。
やや年季が入ったトタン(鉄部)という塗装面の場合、前回塗装時の残塗料くず、サビやさまざまな汚れの除去を行なう下地調整作業が、まず大切で、ここに多くの労力と時間をかけます。
下地調整作業のことを「ケレン」と呼びます。
これが大きな威力でケレン作業をリードする「カワスキ」
上がハンドパッド。その右がマジックロン。そしてゴミを掃くラスター刷毛。
金属製のデッキブラシ。
残塗料くず、サビやさまざまな汚れを掃除機で吸込むと……
こんなにたくさん取れます。
そして要所要所を下塗りサビ止めしたあと
屋根全体にローラーを転がして、さらに下塗りを行ないます。
塗装面の状態によっては、下塗り後もさらにケレン作業を加えて、
さらに下地を整えます。
下塗り塗料が充分乾燥すれば、いよいよ中塗り塗料サーモアイSiの出番。
乾燥前ですが美しい中塗り塗膜ができました。続いて仕上げの上塗り工程に進みます。
が、ここまでで、いったん「塗料サーモアイSiとケレンの、割りなき関係」のお話は終わりです。
このあとは、美しい中塗り塗膜に、さらに美しい上塗り塗膜が加わり、素敵な仕上がりが予想されます。
しかし、美しい仕上がりを支える、地味ですがとても大切な「ケレン」にも、ぜひご注目を。
表舞台で目立つ塗料と、その下に隠れるケレンの分かち難い関係こそ、
塗装工事における、仕上がりの決め手のひとつなのですから。
サイディング外壁のコーキング(シーリング)
2013年12月10日
サイディングボードの間にある繋ぎ目に、ゴムを流し込む事をコーキング(シーリング)と言います。
ここにゴムシールを打ちこむことで、風や雨水などが隙間から入り込まないように出来るので、一見目立ちませんがとても大切な部分になります。
コーキング打ちこみの流れとして、まずは古いコーキング材を撤去します。カッターでボードとシールの間を切り、剥がしていくのですが、この時にボードにあまりにもシールが残っていてもまずいので、出来るだけボード近くにカッターを差し込んで撤去します。
そのあとに、目地の横に養生テープを貼って行きます、しっかりと指で押さえて、ボードに密着させます。少しレンガのように段差があるので、そこにもしっかりとテープを密着させます。
例えば、まっすぐそのまま貼ってしまうと、凹凸に合わせてへこんでいる部分が浮いてしまうのですが、しっかり貼り付けられていないとゴムを均した時に養生テープの下に抜けてしまって、上手く出来なくなってしまうからです。
新築の時は、このシーリングの上から塗装はされていません。
塗装をしなくても丈夫なシール剤を使用しているので数年は平気ですが、やはり上から塗装をしていないむき出しの状態では、シールに紫外線や雨風の汚れなどが全て直接あたってくるので、劣化は免れません。

シールを紫外線などから守り、雨漏りや隙間風から家を守るためにも、新しくシールを打ち替えた後は上から塗装をすることをオススメします。そうすると、シールがむき出しの時よりも断然長持ちするからです。
サイディング外壁のコーキングについて詳しくはこちら
スレート屋根塗装に縁切りは必要なのか真実を知る。
2013年11月29日
住宅の屋根塗装で一番種類が多いスレート屋根。その際、多くの方が気にされる縁切りと言う作業。
業者さんによっても必要・不必要と見解が違うことも少なくなく消費者側からすれば悩まれる方も多いかと思います。
まず、新築からはじめての屋根塗装であれば、十分な隙間がある場合がほとんどなので縁切りは必要ないでしょう。

十円玉が入るほど隙間がある縁切り不要なスレート屋根も少なくない
それでも安心感を得るというためだけに縁切りをしたいという方もいます。
2回目以降の屋根塗装の場合は、それだけ塗装による厚みが増しているため、スレートの重なり部分もふさがってしまう可能性が高くなります。
そのような場合タスペーサーと言う縁切り道材料が便利です。
水切りカッターやカワスキ等での縁切りでは、完全に乾燥硬化していない塗膜は、再びくっついてふさがってしまうからです。

カワスキでの縁切り
ただしタスペーサーの使用はスレート屋根のひび割れのリスクを高めてしまうということも考慮しなくてはいけません。

タスペーサーを挿入して塗装
特にノンアスベストのスレートの屋根材は、ささくれやミルフィーユ層になっていてとても衝撃に弱いためタスペーサーはもちろんのことカワスキ等のヘラを重ね部に際込むこと自体クラックの危険性が高まります。
そもそもノンアスベストの代表例であるニチハのパミールやクボタコロニアルNEO、松下電工のレサスなどは屋根塗装自体が不向きと言われています。

ノンアスベスト屋根の代表格、ニチハのパミール
そしてタスペーサー使用の場合、通常の強固なアスベスト入りのスレート屋根だとしてもクラックの危険性は常にはらんでいます。
まず施工時に作業中に職人がタスペーサー部分を踏んでしまいクラックが入ってしまうケース。
これは職人の注意で避けられそうなイメージがありますが、複数人で作業している場合や突貫的な工事ではついついその上を踏んで歩いてしまうというものです。
そして一番危惧するのが次回の屋根塗装時の場合です。
塗装して10年ほど経過すればスレート自体も新築時と違い脆くなってきます。
屋根全体も風化してタスペーサーの取り付け場所も差し込み当時よりかは不明瞭になってくる可能性も高く、そもそもその時に作業する職人はほぼタスペーサーのことを気にすることもなく作業してしまうことが大いに予想できます。

タスペーサーを挿入した後、その上の歩行は要注意
そうなってくるとパキバキとクラック音を立てながら作業することになってしまいます。
更に屋根に上るのは塗装業者だけではありません。
テレビアンテナの不具合などで電気屋さんがのぼる可能性もあります。
足場なしでハシゴだけで上る訳なので歩行箇所を気にする余裕などはまったくといって無いとも思われます。
しかし遮熱や断熱など、塗料性質上どうしても肉厚になってしまう屋根塗装に関してはそれを見越したとしてもタスペーサーは必要になると思います。
また、断熱塗料であれば十分な弾力性があるので、問題ないと思いますが、そこは実際に現場を見ている業者さんによく訪ねてみましょう。